History伊万里焼の歴史


日本磁器の発祥
日本で最初に磁器が焼かれたのは、現在の佐賀県西松浦郡有田町とされています。
豊臣秀吉の朝鮮出兵のときに、肥前国の鍋島直茂(佐賀藩の藩祖)は、朝鮮半島から陶工たちを日本に連れてきました。その中にいた李参平は、中国景徳鎮のような白い磁器の原料となる陶石を求めて多久領内、鍋島領内を巡ったのち、有田の泉山で良質の白磁石を発見し、1616年(元和2)焼成に成功したといわれています。
現在、李参平は有田の「陶祖」として、陶山神社に祀られています。
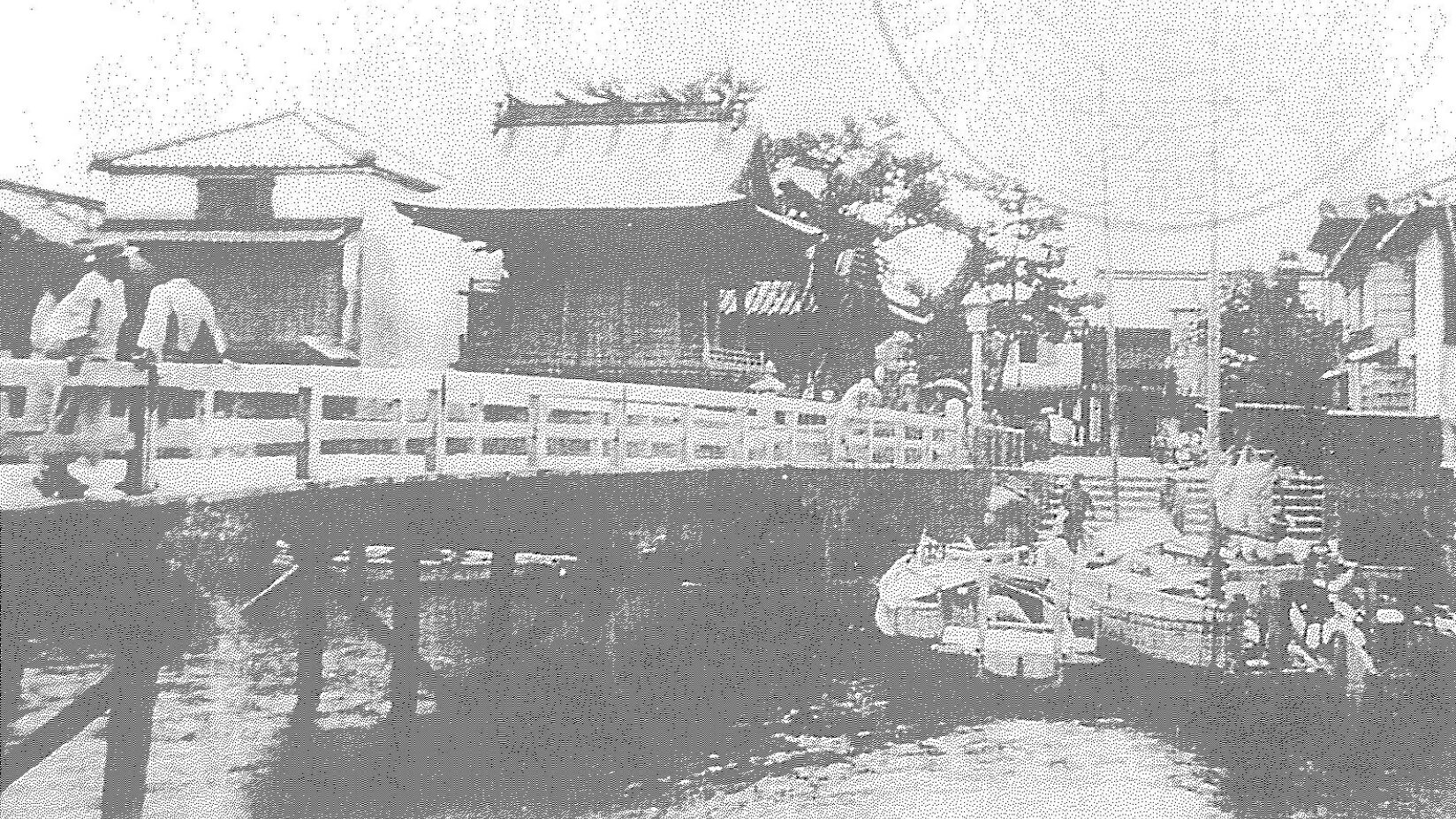
古伊万里の輸出
1602年(慶長7)に設立されたオランダ東インド会社(VOC)は、ヨーロッパや東南アジアへ中国磁器を輸出していました。ところが、中国では明朝から清朝への交代で内乱が発生し、磁器の輸出ができなくなりました。
困ったVOCは、そのころ生産が活発化していた有田に目をつけ、日本と輸出契約を結びます。当時、日本は鎖国中で、海外と唯一の窓口は長崎の出島でした。1659年(万治2)、伊万里港から積み出された焼物は出島へ向かい、オランダ船に載せ替えられ海外へと旅立ちました。この後、約100年にわたり伊万里焼の輸出は続き、ヨーロッパの王侯貴族などを魅了しました。

陶器・磁器
現在の伊万里市内においては、大川内山の磁器だけでなく、江戸時代から南波多、大川、松浦などで陶器も焼かれていたことがわかっています。


鍋島藩窯
江戸時代、佐賀鍋島藩は伊万里の大川内山に官営の御用窯(鍋島藩窯)を作りました。そこで焼かれた焼物を「鍋島焼」と呼んでいます。
鍋島藩は、関ケ原の戦いにおいて豊臣側についたため、徳川の時代では外様大名でした。譜代大名に比べればその地位は不安定で、いつ取り潰し、配置換えになるかわからなかったのです。
そのため、当時長崎港の警備をしていたことで、出島を通して入ってくる中国磁器などを将軍家に献上していました。
しかし、中国の内乱で磁器が入ってこなくなると、藩は自らの手で焼物を焼こうと、1628年(寛永5)に有田の岩谷川内で窯を築きます。その後、1661年(寛文8)有田の南川良に移り、1675年(延宝3)に現在の地である伊万里の大川内山へと移ります。
藩窯では、製法の秘密漏洩防止のため関所が設けられ、陶工は有田の職人から選りすぐりの技術者を集め、腕が落ちると入れ替えが行われるなど厳しい管理が行われていました。半面、武士と同じように給料をもらい、名字も名乗れるなど、身分も保証されていました。
藩窯の焼物は、皇室や公家、幕府の将軍家への献上品、諸大名への贈答品、自藩の城中品のみが生産されましたが、1871年(明治4)の廃藩置県により終わりを告げました。
鍋島焼は、最高の品質を求め採算を度外視して生産され、一般に流通することがなかったため、明治になるまでその存在を知らない人が多く、より一層の価値を高めています。

副島勇七伝説
1780年代、名工だった副島勇七は、職人気質の性格から役人に歯向うことも多く、ついには御用職人の資格をはく奪され、正力坊村に追放されました。困窮した勇七は妻子を捨て、密かに村を抜け出して行方不明となります。
その後、勇七は伊予の国(愛媛県)砥部に移り住み、陶工の仕事を続けました。その砥部焼は、京都や大阪で評判となりますが、鍋島焼の秘法漏洩を恐れ勇七の行方を捜していた佐賀藩の下目附、小林伝内の目にとまります。呉須売りに変装した小林は勇七を見つけ出して捕らえ、佐賀まで連れ帰りました。鍋島焼の秘法を漏らしたという罪で、藩主茂治もその技術を惜しみ死罪を減刑してやりたいものの、藩法に例外を作るわけにもいかず、1800年(寛政12)に嘉瀬川の刑場で打ち首となり、大川内の鼓峠に晒し首となりました。
その後、勇七の首は大川内山に葬られましたが、陶工の誇りとして参拝が絶えなかったと伝えられています。

明治以降の伊万里焼と大川内山
明治になり、廃藩置県で職を失った陶工たちは、鍋島焼の復興を図るため精巧社を設立、鍋島家の御用窯となりました。
明治晩年から大正にかけ、大川内では火鉢、花器、床置物や盃、茶器などの小物を製造していました。
その後も、伊万里焼は時代の変遷に合わせ脈々と続いてきましたが、1984年(昭和59)には鍋島藩窯公園が完成、2003年(平成15)には鍋島藩窯跡として国の史跡指定も受け、今では「秘窯の里 大川内山」と呼ばれています。
現在、大川内山には約30の窯元があります。江戸時代からの子孫もいて、鍋島焼の伝統を守りながら続いている窯元もあれば、現代風にアレンジした焼物を作る窯元もあり、多くの焼物ファンが訪れる伊万里の観光名所となっています。